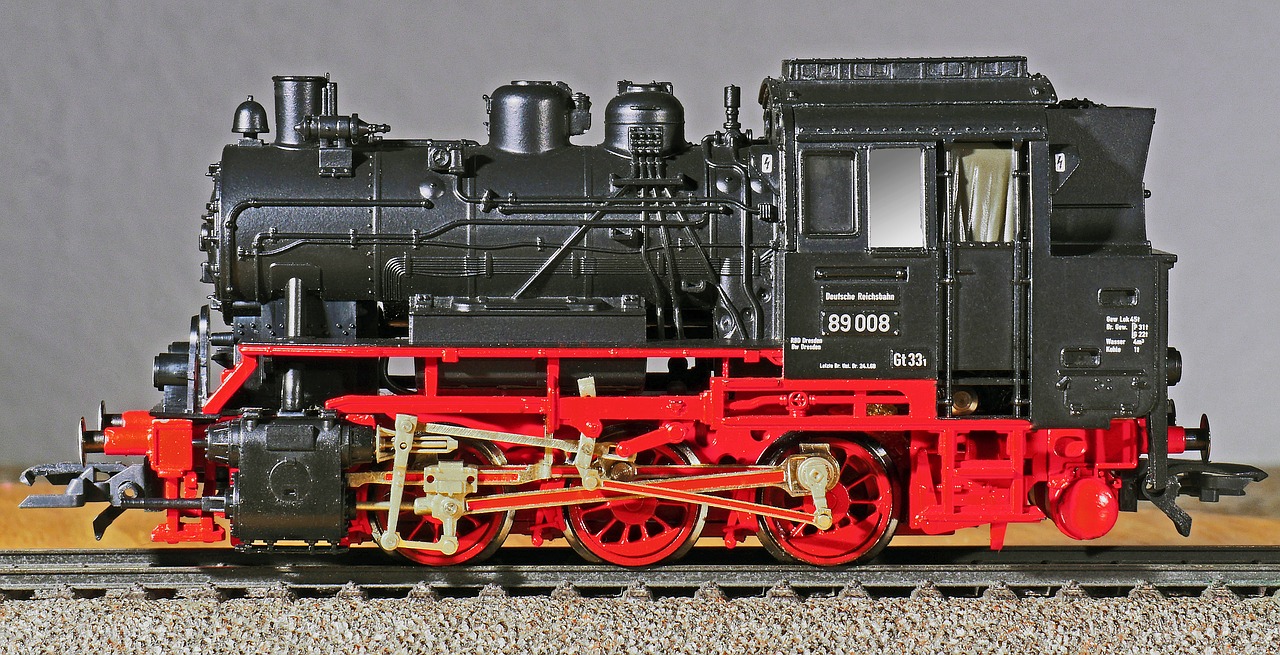
hpgruesen / Pixabay
慶応2年(1866年)、横浜で発行されていた、週間英字新聞「ジャパン・タイムズ」に匿名で掲載されたある論説が、徳島藩士・沼田寅三郎によって翻訳され、「英国策論」と題して出版された。
日本が国際社会に登場するためには、今の幕藩体制ではだめで、天皇を頂点とし強力な諸大名を中心とする中央集権国家をつくるべきだというのである。
記したのは若干22歳のアーネスト・サトウである。
サトウ、通訳から書記官に
アーネスト・サトウは初代公使・オールコックの口添えで日本にやってきたが、着実に仕事をこなして通訳官から書記官に昇進し、オールコック公使とそれに次ぐパークス公使の通訳、秘書として活躍した。
サトウは薩英戦争・四国艦隊下関砲撃事件に同行し、薩摩・長州藩と接触した結果、両藩が外国との貿易を望んでいることを知り、幕府の虚言(薩長が開国政策を妨害している)に不信感をもった。
そして彼の助言もあり、パークスは薩摩・長州藩に接近するようになった。
サトウ、一家言もつ外交官に
日本語に堪能なサトウは、幕府側、倒幕側両者の意見を聞く重要な場面にしばしば同席したため、政局の全体像がよく見えた。
一方の陣営にいるものにとって、相手の陣営の動向は読みづらい。すでにサトウは単なる通訳ではなく、一家言をもった外交官であった。
したがって、倒幕派の志士や大名、あるいは幕府高官がサトウの意見を求めて集まってきたのであった。
サトウは天皇をはじめ、幕府側の徳川慶喜にも、倒幕派の西郷、大久保、岩倉、桂、高杉、井上、伊藤ら名だたる面々に直接会って、腹蔵なき意見を交換している。
西郷はサトウの著作であると知らず「英国策論」を読んで感激した。以後これが彼の基本姿勢となった。ただこんな若造の著作だったかといって軽視せず、本質だけを見ているところが潔い。
西郷に決起をうながす
西郷ら倒幕派に決起をうながしたのもサトウである。
西郷は情に動かされやすい。身内でもないのに日本の未来に心を砕き、「あなた方薩長が新しい体制を創らなければ外国の餌食になってしまう」と真剣な目で迫られると、心が動くのである。
竜馬に「長州がかわいそうではないか」と迫られ、薩長同盟に踏み切ったし、山岡鉄舟に「命も要らぬ、名も要らぬ」といわれ、江戸無血開城に同意した。
ただし西郷は、欧米の軍事介入を恐れ、イギリスの軍事援助だけはご免こうむると、くぎを刺したという。
アーネスト・サトウの見た日本
サトウのように予備知識をもたず、各方面の指導者に会って通訳をしていると、この国の構造がわりと鮮明に見えたのではないか。
彼は来日してほどなく、徳川将軍が皇帝ではなく、大名のなかの最大勢力にすぎないと見抜いた。
さらに今の幕府にはもはや牽引力はなく、オランダが去ったあと、将軍家に急接近しているフランスを批判的な目で眺めている。
そしてフランス公使ロッシュが諸藩を顧みず、幕府だけを支援しているのに対し、イギリス公使パークスは、サトウの意見を容れ諸大名とも広く付き合い、表面上は中立の立場をとったが、水面下では薩長に接近していた。
その結果、イギリスの動向は倒幕、新政府樹立という流れを後押しする形となった。
こうしてサトウは20~30代のもっともタフな時期、見識あるイギリス人外交官として、幕末から明治維新の重要な外交交渉に登場し、維新政府と西洋との懸け橋の役割を果たした。
サトウは後日、この時期が人生最良の日々だったと述懐しているが、劇中の人物たちと直接行き来しながら、すぐそばで活劇を見物しているような気分であったろう。
明治政府の冷ややかな外国人対応
明治28年(1895年)から6年間は公使として再来日したが、すでに明治政府の改革は一段落した状況であった。
この時期、明治政府に厚遇されてきた多くの外国人技術者、教師たちは、つぎつぎに解雇されていた。高給を払わなくても、自前でやれるようになったからである。
しかし長年、情熱を捧げてきた外国人たちにとって、感謝の言葉すらなく、突然の解雇通知は大きなショックであった。
他国では、そのまま住み着いて快適な人生を送るケースもあるというのに、あまりに冷たい仕打ちではないか。
サトウも同様であった。
幕末、明日の日本について語り合った友人たちはすでに政界を去り、今やサトウに声をかける者すらいない。彼もまた、冷ややかな政府の対応に失望したひとりであった。
イギリス帰国後のサトウ
明治39年、サトウは帰国後、外交官生活から引退し、イングランド南西部デボン州に隠棲した。日本のことを忘れようと努めたのか、他人に日本の話しはほとんどしなかったという。
彼は日本滞在時、武田兼を内妻とし3人の子をもうけた。入籍はしなかったが子供らは認知して経済的援助をつづけた。イギリスに帰ってからも独身を通したという。
また、次男をロンドンに呼び寄せ植物学者として育て上げた。のちの日本山岳会会長で、「尾瀬の父」と呼ばれた植物学者の武田久吉博士である。
サトウは後半生の22年間は、読書とガーデニングを趣味として暮らした。晩年(昭和4年)は孤独に耐えかね、日本に移住しようとしたが、病に倒れ86で他界した。
男子の本懐
サトウは日系と間違われやすいが、スラヴ系の名字で「Satow」というのが本当である。
18歳のとき「エルギン卿遣日使節録」を読んで日本に憧れ、翌年の文久2年(1862年)にイギリス外務省へ通訳生として雇われ、同年、駐日公使館の通訳生として横浜に着任した。
着任1週間でいきなり生麦事件がおこり、その後イギリス船にのって薩英戦争に加わった。
そのまま革命前夜の日本で、公使の片腕となって縦横無尽の活躍をしたのである。
その彼が誰からも若造と侮られることがなかったのは、時間を割いて日本語と書道をマスターし、外交交渉では通訳で終わらず、つねに自分の見識を高めていった努力の賜物であろう。
男子の本懐といえるのではないか。


